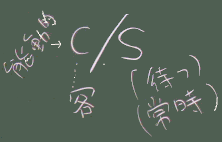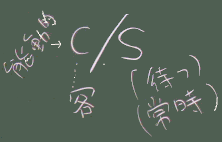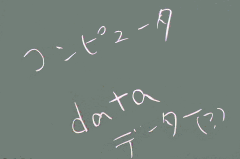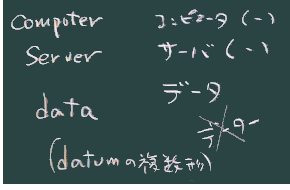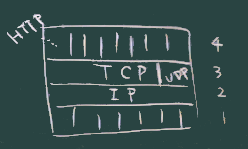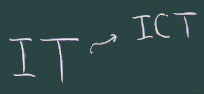TCP/IP 概論(BNS 補助資料 1
序論)
1 クライアントとサーバの関係
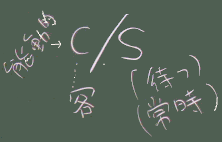 C/S
C/S
- 商店(でも何でも)でいえば
客(クライアント)と店員(サーバ)の関係に相当する。
- 「サーバ」という用語は、サーバ機(ハードウェア)の意味でもサーバソフトウェアの意味でも使われる。
(混乱しないように)
- サーバで提供されている機能が「サービス」である。
- 昨今はWeb技術を利用したサービスが主流になっている。
(がそれ以外のユーザ向けサービスもあるし、インターネットの根幹を支えるためのサービスもある)
補足) 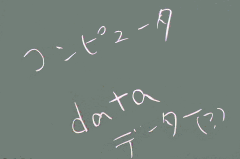
- 「サーバ」という単語は、上記以外にも(情報システムに限定せず)様々な意味がある。
- 「サーバー」と表記されることも多いが、
情報システム用語では「サーバ」表記がよく使われる
(でも口語では「サーバー」と伸ばして話されることが多いが)。
- この傾向は「コンピュータ」についても同じ。
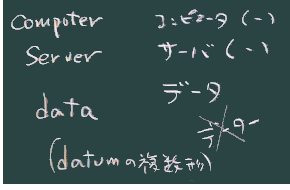
- ただし、「データ」という単語は、
伸ばして発音すると(伸ばして書くともっと)恥ずかしい(右図)。
2 TCP/IPとは何か
- 現在世界的に主流となっているプロトコルスイート(スイートは「甘い」ではない)
- 昔は大手コンピュータメーカーがそれぞれ(IBMのSNAと、各社それに対抗したもの)策定していた。
標準としてOSIが作られたが結局はTCP/IPが生き残った。
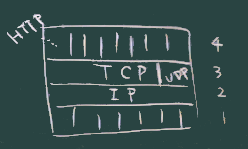
OSIはOSI参照モデル(7階層)として名を残した。
- TCP/IPは4階層で作られている。
名前について(補足)
- TCP、IP
といった単語は、それぞれがプロトコル(規約)の名称(ググってみてください)。
- TCP/IPは、それに含まれる多数の規約のうち最も重要な位置を占める2つのプロトコル名を
つないだだけの名前。
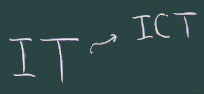
- これらは、英単語だと思わずにアルファベット読みするのが普通。IPを「イップ」のように
読むと恥ずかしいので「アイピー」でいい。
- ただし、スラッシュは読まない。カナで書くと「ティーシーピーアイピー」だが、
急ぐと「ティシピアイピ」ぐらいに発音されることもあるだろう。