%情報学概論Ⅱ
第1回
%企業情報学部
%4/14
## 情報学概論2 第1回(4/14)
(Introduction to Informatics 2)
## 1 はじめに
(第1,2章は IIn1 とほぼ共通の事項)
+ 平岡信之 自己紹介(略)
+ プリント(等)の置き場所
http://www2.nagano.ac.jp/hiraoka/IIn2/
レジュメは印刷配布はしない
(必要に応じて各自で印刷できる…けど画面で見るほうが効率的)
***
* LMS は使わない見込みです(ご了解ください)。
* 出欠データは自己管理のために活用ください(成績には反映されないので)。
---
##### 補足
* 「講義資料庫」にも(間接的な)リンクが置いてあるのでダウンロードして使っていい。
* ここに置いてあるのは右上図に示すような種類のファイルです。
* このURLにいつでもアクセスできるようブックマークしておくといいい。
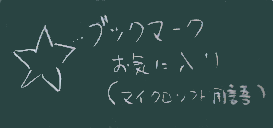{.tiny}
---
* ブラウザには「補完」の機能があるので(「www2」で始まるアドレスは昨今はさほど多くないこともあり)
* 一回このアドレスにアクセスしたことがあれば、
* 次回以降はアドレスバーに最初の4文字を入力すれば上記アドレスが候補として提示され(選択可能にな)る筈なので
その方法を専ら使うというのでもOK。
### 授業の位置付け:
+ IIn1 とともに、学部の様々な技術系科目群の基礎となる科目
+ なので登録必修
+ IIn1が前提科目となっている
* 基礎教養科目「コンピュータ基礎」と相補的関係
* マウスを使うコンピュータ基礎
* マウスをあまり使わない情報学概論
* Ⅰ、Ⅱと2年に分けて履修するその後半部
### 目的と概要
+ 知識と技能をバランスよく
1. 情報とは何か
2. コンピュータの効率的操作
+ プロに至る道筋
(単一のアプリケーションに習熟するよりは...)
1. 組み合わせる技術
2. 使い分ける技術
### 授業の形態
+ 大枠としては講義形式だが、
+ 調べたり考察したりして、
+ わかったことなどを報告する、というサイクルを多用する。
+ コンピュータを実際に操作してみる技術的実習も行う。
## 2 受講の要件
***
#### パソコンは毎回必携
* もちろんネットにアクセスできること
* レジュメの閲覧、メールの読み書き 等だけならスマホでも(たぶん)可能
(画面の狭さを厭わなければですが)しかし、
* プログラミングはキーボードがないとほぼお手上げ
+ 部屋の電源コンセントの数が不足しているので、各自、
(この時代のマナーの1つとして)二股コンセントかテーブルタップを
PCのACアダプタと一緒に携行(する習慣をつけるように)して下さい。
---
#### コミュニケーション
* オフラインでのコミュニケーションも重要
+ 平岡は4限がオフィスアワーの予定、ですが
* 授業前はお互いにばたばたします。よかったら授業終了後に。
---
##### オンラインも
+ 伝統的にはメールが使われてきている。
* (原則として大学のアドレスを使ってください)
* 平岡のアドレス: hiraoka@nagano.ac.jp
* 件名の先頭に (IIn2) と書いておくこと
(内部的にIIn2という略号を使ってます)
* 課題提出もメールを原則にします
***
* チャットも使いましょう(トップページにリンクあり)
* リアルタイムのコミュニケーションとして重要(もちろん口頭でもOKだが)
* 入って、何かひとこと発言してみてください。
* 雑談、授業中に思ったことをぼそっとつぶやく、など(SNS的な使い方?)もあり
(先生には見えてしまうけど)
---
#### その他 環境の準備 と心構え
+ おぼえた技術は(でもすぐ忘れるんだよね)メモしましょう。
* いきつけの サーチエンジン 辞書サイト(英和・和英 技術用語など)
* ブックマーク(別名 お気に入り)の活用
## 3 IIn1(昨年度)のおさらい
* 昨年度のIIn1の[期末試験の問題](IIn1/mondai.pdf)を眺めてみよう。
* Markdownの使い方と文法を覚えていますか
+ 昨年は Atomとそのプレビュー機能などを活用しました。
が、今年は違う道具を使うことにします(後述)。
* 文法はWebに情報源が沢山ありますね。
***
* (参考資料)たとえば本ページのソースは [1.md](1.md)(ファイルの拡張子 .html を.md に変えた名前)
というファイル名で参照可能。
* コマンドプロンプト(或いは昨年度使った他のアプリケーション)は起動できますか。
* マウスなしでも大丈夫?
## 4 実習環境準備(確認)
***
#### テキストエディタ
***
:::{.rcolumn style="width: 50%"}
* Atom エディタの状況:
1. [開発が終了した](https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1457313.html)。
2. 最終版の証明書が[不正アクセスにより無効化され](https://news.mynavi.jp/techplus/article/20230201-2581120/)、
使うなら1つ前の版に戻す必要があるらしい。
* その背景:
* [GitHub](https://github.co.jp)(ソフトウェア技術者のためのリポジトリサイト)が
Atom エディタを提供していた。
* GitHub を [MicroSoftが買収した](https://wired.jp/2018/06/07/microsofts-github-deal/)
* Microsoft は 以前から VSCode を提供していた(Atomはソフトウェア投資としては重複する)。
:::
***
* Atom に代わるテキストエディタを見つけておこう。
* 移行先について[考察したサイト](https://www.qbook.jp/column/20220630_1365.html)も参照ください。
* 他に、[Pulsar](https://pulsar-edit.dev) も注目されている(Chocolatey
にはあるが今のところ Scoopでは提供していない)。が、
* ここでは、[VSCode](https://azure.microsoft.com/ja-jp/products/visual-studio-code)を推奨しておきます。
* IIn1 で使った hex-editor 拡張機能(と同じもの)が VSCode でも使える
(今年も授業で活用します)。
***
* VSCode は、
* [Scoop](http://scoop.sh) で導入するのをおすすめします(でもChocoでも大丈夫そうです)。
* 一般的にこの名前で認識されているが、本名は「Visual Studio Code」のようです
(Windowsで名前で呼び出してVSCodeを起動する時などは長いほうの名前で)。
* Scoop については、[この解説](../ANY/scoop/html) を参照ください。
#### データ転送
* sftp で www2.nagano.ac.jp に接続できますか。
* 去年はトラブルにより代替サーバを使ってもらいましたが、
* 今はアカウントが整備された筈
* FileZilla か WinSCP で接続を試みておいて下さい
## 5 (さっそくだが)演習(自己紹介を兼ねて){#hw}
以下の内容の簡単な文書を、Markdownで書いてみてください。
1. 私の自己PR(と、郷土自慢も)
2. 私の大学生活
3. 私とPCのつきあい(どんなアプリケーションを使っているか、など)
* hiraoka@nagano.ac.jp あて メールで提出