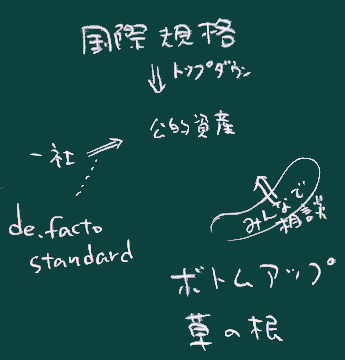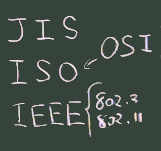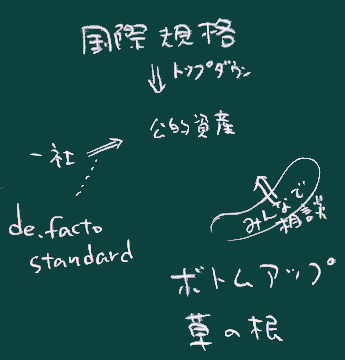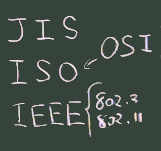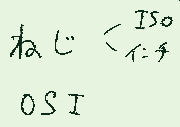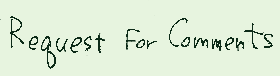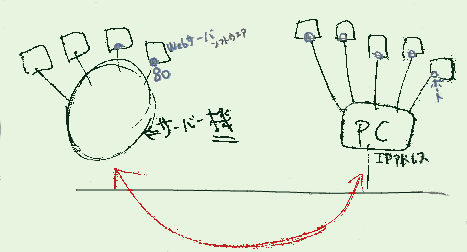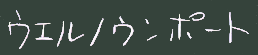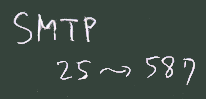アプリケーション層(予備知識)(BNS
補助資料)
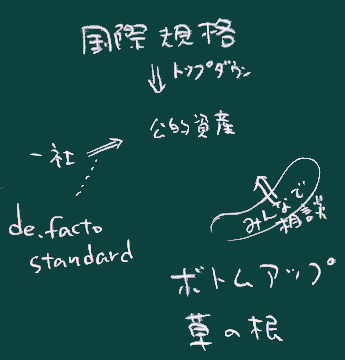
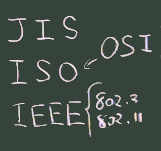
1 規格について
- 工業製品の規格は、公的規格団体(JIS ISO ANSI CCITTなど)や、
学術団体(IEEEなど)、工業団体(EIAなど) が策定することが多いが、
- インターネットの規格は、ネット内で話し合いで決められている。
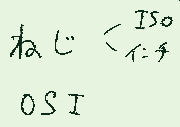
- (余談だが)ISOは様々な国際規格を策定している有力な組織だが、必ずしも統一された規格に結びついている訳ではない。
- 例えば
ネジの規格がいくつか(我々に身近なコンピュータでも)使われていたり、
- OSIというプロトコル体系は(TCP/IPに席巻される形で)OSI準拠の製品が作られなくなり、参照モデルとして
の意義だけが残るに至っている。

- その草案(のちに確定版になったものも含めて)が RFC
と呼ばれている。
- それぞれの技術に関する文書は、RFCの一覧 や 日本語に翻訳されたRFCの一覧
から探すことができる。ただし、
- 例えば SMTP、HTTP といったプロトコルに関して、
(拡張規格ではなく)土台となる規格は、SMTP HTTPという
(普及したことにより略号で通用するようになった名前でなく、
文書の題名が「HyperText Transfer Protocol」のような長い名称で
書かれているので検索するときには注意が必要。
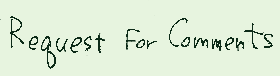
2
ポート番号とその文字表記について
- ポート番号については、第4回で行った解説も参照。
- 一般に、1台のコンピュータで同時に複数のソフトウェアが動作している。
- すなわち、当該コンピュータに到達したIPパケットが、
どのソフトウェアに届けられるかを決定する仕組みが必要で、
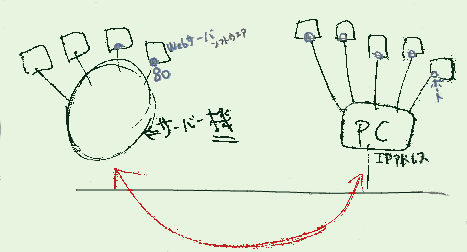
- そのための識別番号が、ポート番号(なのでTCPヘッダに書かれている)。
- IPアドレスはコンピュータ毎に付与される(正確には、ネットワークデバイス毎)アドレスであることを想起すること。
- 接続先のポート番号を指定する場面で、番号でなく名前で記述する
ことができる。
- netstat コマンド等の表示でも(-n オプションを付けなければ)
名前で表記されている。
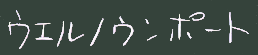
- 様々なサービスで、通常使われるポート番号を、ウェルノウンポート
と呼ぶ。HTTPなら80番、SMTPなら25番、などが慣習として使われる。
(ただし最近は、クライアントからの送信には25番ではなくサブミッションポート587番
が使われる傾向がある)
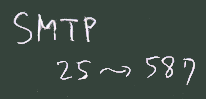
- ウエルノウンポートについては、一覧のページや、
自分のコンピュータに内蔵された /etc/servicesファイル
を確認されたい。
- ssh
などの(多くの利用者からのアクセスを前提としない)ネットワーク機能では、
セキュリティ上の理由から、故意に慣習からはずれたポート番号を使う、
というケースもある。