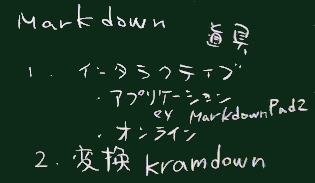
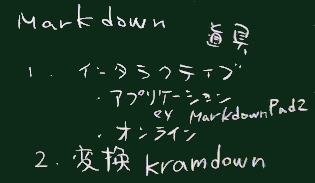 |
| 道具の分類 |
同上
cinst markdownpad2 -y
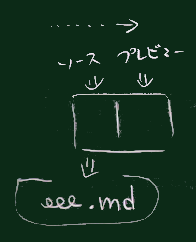 |
| markdownエディタ |
または配布元などからダウンロードしてインストール
コマンドプロンプトで
gem install kramdown
(Slimを入れたときと同じ proxy設定要)
kramdown コマンド
kramdown -h
:: この出力(使い方説明)は長すぎて流れていってしまう可能性がある
kramdown mdソースファイル名
::
kramdown mdソースファイル名 > html出力ファイル名
SLIMの中に埋め込む:
以前(SLIMの紹介時)に提示した例section)や、SLIMファイルにあるように、
markdown:
## markdownの例
ここにあるようにmarkdown部を2文字分字下げする
という書き方をしておくと、slimrbコマンドで変換でき、 * SLIM(ページ全体の構成を記述する)と、markdown(原稿を書く)を1つのファイルで併用できる。 * このとき内部で必要に応じてkramdownなどの補助的プログラムが呼び出される。
rakeファイルにルールを記述する:
以前に作ったrakefile.rb に、以下のような行を記述すると、(SLIMの時と同様に) rakeコマンドで自動的に変換される。
MSRCS = FileList["*.md"]
MOBJS = MSRCS.ext('html')
## この2つの大文字の名前は、rakefileの内部で
## 変数名として使われるものなので
## 名前は何でもいい。ただし、上記のMOBJSは
## 以下の行でタスク名の1つとしてもう一度使う。
task :default => SOBJS+MOBJS
## SLIMのタスク名 SOBJS とともに、MBOJSも有効にする
rule '.html' => ['.md'] do |t|
sh "kramdown #{t.source} > #{t.name}"
end
## この3行で変換の方法を具体的に示す
kramdownを(コマンドではなく)rubyのライブラリとして使う:
以下にプログラムの例を掲載する。
(詳細の説明は省く)
#!ruby -Ku
require 'kramdown'
cssName= 'default.css'
incName= 'inc.html'
puts <<EOS
<!Doctype html>
<meta charset="utf-8">
EOS
File.exist? incName and puts File.open(incName).read
File.exist? cssName and
puts %Q!<link rel="stylesheet" type="text/css" href="#{cssName}">!
puts Kramdown::Document.new(STDIN.read).to_html