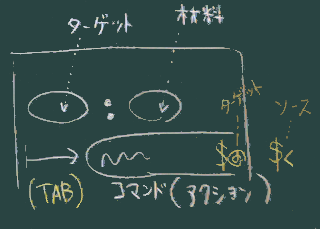情報学概論Ⅱ 第8回
企業情報学部
6/3
情報学概論2 第8回(6/9)
(Introduction to Informatics 2)
0 はじめに(事務連絡など)
成績評価について:
![加点法]()
- 当科目では主に提出物を中心にして加点法で成績評価をします。
- 期末試験も(感染状況により突発的な変更の可能性はありますが)行われる予定ですが、試験も、加点法の成績評価の一環だとご理解下さい。
- レポート課題についての考え方:(昨年こんな資料を提示しました)
- 前回の補足(日の丸を数値で指定して作るいくつかの方法について)
1 作業の自動化(その3)
1.1 コンテキストメニュー
- 前回作った .bat ファイルの呼び出し方を、さらに探ってみる。
- コンテキストメニュー
![regedit]()
- Windowsでは、レジストリを直接操作することで項目の追加が可能
- (だが煩雑なのでお勧めはしない)代わりに、
- 「送る」メニュー
![sendto]()
- ここに登録することならさほど困難ではないので紹介しておく
1.2 ビルドツール(Make と Makefile)
- プログラミングでは重要な作業であるため、最近は、
![makeの仲間]() ビルドツールは各プログラミング言語ごとに整備されている。
ビルドツールは各プログラミング言語ごとに整備されている。
- たとえば ruby 用に rake がある。
- rake は(単語の意味としては熊手だが)make の名前(の響き)を借用して命名されている。
- 初期のビルドツールとして有名なのが Make。(今も現役)
- 今回はこれを紹介する。
実習
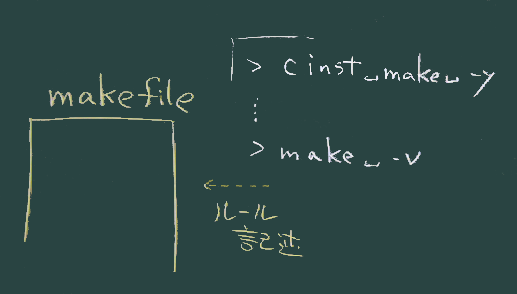
- インストール
- Makefile を作成
- make コマンド(まずはコマンドプロンプトから)
MakeFile の内容
今回は最低限の指定として2つのことを書く
- ルール記述
![makefile文法]()
- サフィックスルールとパターンルール 2つの書き方がある
%.html:%.md pandoc -o $@ $<
この2行目(アクション行)は Tab文字でインデントする必要がある
(エディタによってTabが複数のスペース文字に分解されないように)。
- Atomの場合、(編集メニューから)文法「Makefile」を選択しておくといい。
- ターゲットを指定して呼び出す
例えば、現在のフォルダ(makefileが置かれている)に、 ソースファイル aaa.md があるとすると、
ソースファイルの拡張子を
.htmlに置き換えてそれを ターゲットにする。
make aaa.html
2. 課題
以下の2つを各自で実施しておいて下さい。(できたかどうか報告下さい)。
make (GNU Make)をインストールする
(導入の方法については、このアプリケーションの名前をヒントに検索などで調べてみて下さい)… でも
scoop install makeが一番楽そう。上記にサンプルとして示した2行の内容で Makefile を作成する。
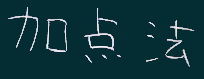
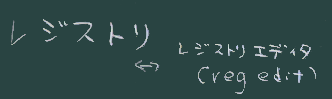
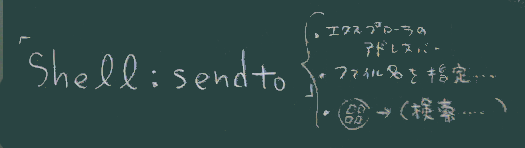
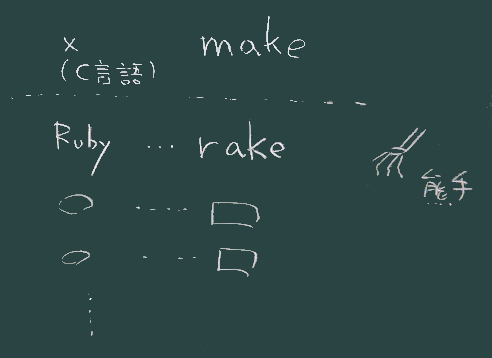 ビルドツールは各プログラミング言語ごとに整備されている。
ビルドツールは各プログラミング言語ごとに整備されている。